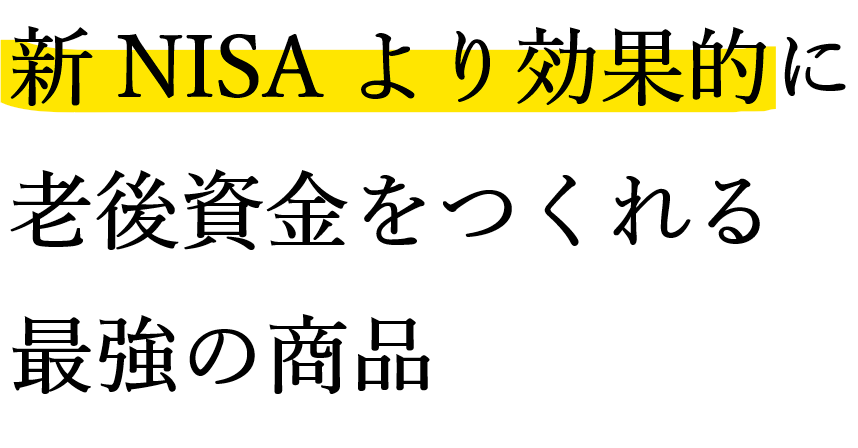(例)大卒22歳で就職、運用38~48年で試算してみましょう。
これについて、
iDeCo一時金、会社退職金(一時金)の間隔を
①5年とした場合と、
②10年超とした場合で
税負担の違いを比べてみましょう。
<比較の前提>
1.積立開始:22歳
iDeCo受け取り:60歳時点、一時金で2,000万円
退職金受け取り:
ケース①65歳、ケース②70歳、一時金で2,000万円
勤続年数:22歳から65歳(退職年齢)まで(iDeCoの場合は会社勤続年数ではなく、通算加入年数を基礎に控除額算定)
60歳時点:勤続38年/65歳時点:勤続43年/70歳時点:勤続48年
退職所得控除の計算式:
20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得金額=(受け取り額-控除額)÷2(マイナスの場合はゼロ扱い)
ケース① 60歳でiDeCo2,000万円 → 65歳で退職金2,000万円
(1) 60歳 iDeCo
勤続年数=38年
控除額=800万+70万×(38-20)=800万+1260万=2060万円
受け取り額=2000万円
退職所得金額=(2000-2060)÷2=マイナス→0円
iDeCoについては非課税。
(2) 65歳 会社退職金
勤続年数=43年
控除額=800万+70万×(43-20)=800万+1610万=2410万円
ここで「10年ルール」により調整が必要。
60歳でDC一時金を受け取りっており、その後65歳は10年未満(5年後)なので、控除額が重複調整される。実際には、60歳時点の38年分が既に控除で使われているため、「43年-38年=5年分」しか新たに退職金側の控除に使えない。
控除額=70万×5年=350万円
退職金2000万、控除350万=1650万円
退職所得金額=1650÷2=825万円
ケース①結果
iDeCo課税:0円
退職金課税:825万円
合計課税退職所得=825万円
税額計算:所得税825万×0.23-63万6000=126万1500円
復興特別所得税126万1500×0.021=2万6491円
住民税825万×0.10=82万5000円
所得税 126万1500円
復興税 2万6491円
住民税 82万5000円
税額計 211万2991円(約211万円)
ケース②60歳でiDeCo2000万円 → 70歳で退職金2000万円
(1) 60歳 iDeCo
控除額(38年)=2060万円
受け取り2000万円-控除2060万円=マイナス → 0円
(2) 70歳 退職金
勤続年数=48年
控除額=800万+70万×(48-20)=800万+1960万=2760万円
ただし、60歳のiDeCo受け取りから10年以上(70歳)経過しているため、新ルールでも控除はフルに適用可能。
退職金2000万円-控除2760万円=マイナス → 0円
ケース②結果
iDeCo課税:0円
退職金課税:0円
合計課税退職所得=0円(完全非課税)
税額 0円
5年ずらし戦略(iDeCo60歳受け取り:会社退職金65歳受け取り)では「控除の重複調整」がかかり、税額は211万円。
会社退職金受け取りを70歳まで遅らせれば、非課税で逃げ切り可能です。
だから、iDeCoの出口戦略において会社の退職金の受け取り時期をコントロールすることが最も重要です。