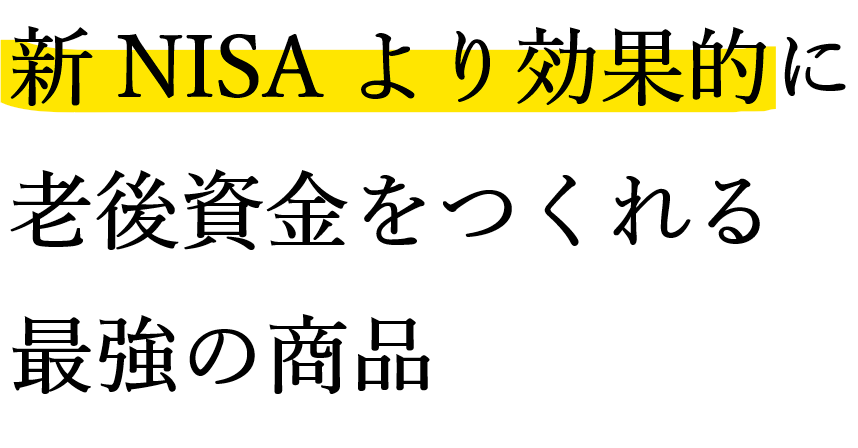積立を長期にわたって続けるためには?
会社員でも個人事業主でも、
積立金額を確保するのが苦しくなって、
積立を減額したり、iDeCoをやめてしまおうと思うときがあるかもしれません。
それを乗り越えるためには、
掛金の節税効果で得た金額を生活費に回さず、
次のiDeCoの掛金として再投資することをお奨めします。
それにより、iDeCoの掛金を増やすこともできます。
現状、60歳まではリターンを受け取れないiDeCoですが、
掛金節税効果は60歳以前に受け取れるという大きなメリットです。
さらに、
還付金を再投資へ回せば、資金計画はさらに強固にできるのです。
このように、
iDeCoの掛金の節税効果であることが大きなメリットなんです。
◆iDeCo改正で、最も恩恵を受けるのは誰でしょうか?
今回のiDeCoの改正で大きなメリットを受けるのは個人事業主なんです。
その理由は以下の通りです。
1.積立金額の上限が大きくなる(年額最大90万円)ので掛金節税効果を最大化できる
2.個人事業主は退職金がないか、あっても、
受け取り時期を自分でコントロールできるので10年ルールを逃れることができる。
さらに、
個人事業主とともにオーナー経営者も自分で退職金の受け取り時期を決められるので、
iDeCoのメリットを最大化することができる。
◆会社員にとってのiDeCoの活用方法
会社員でありながら、どうすればiDeCoのメリットを最大化することはできるでしょうか?
それを検討する前に、10年ルールについて考えてみよう。
◆iDeCo受け取り時の10年ルールとは?
iDeCoがNISAに比べ不利な点である受け取り時の税制について説明しましょう。
iDeCoの受け取り金は課税されるが、
優遇税制である公的年金等控除または退職所得控除が適量されます。
iDeCoのメリットを最大化するには、
受け取り時の税金支払いをゼロまたは最小化すれば良いのです。
◆iDeCoの受け取り額を一時金でもらう場合で説明しよう。
1.退職所得控除適用の受け取り間隔の要件が5年から10年に延長された
2026年1月1日以後、iDeCo一時金受け取り後に、会社退職金(一時金)を受け取る場合、
10年の間隔を空ければ、それぞれの一時金に満額の退職所得控除が適用される。
2.逆に「受け取りタイミングを10年以上ずらさず」
60歳でiDeCo、65歳で退職金、
といった従来型の「5年ずらし戦略」を取ると、
退職所得控除が制限され、税負担が増えてしまうことになります。