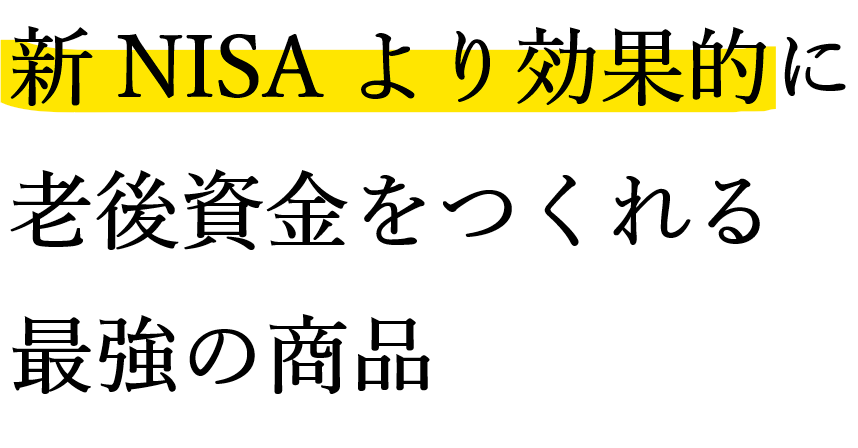会社員のiDeCoの活用方法と10年ルール対策
一般の会社員でiDeCoの受け取り金と会社の退職一時金の間隔を10年超にできる人は、ほとんどいないでしょう。
iDeCoの受け取り金は60歳で受け取るのが最短ですので、会社の退職一時金の受け取りは70歳以降にする必要があるからです。
なので、多くのYouTuber税理士は10年ルールへの移行を「改悪」と言っている。
それでも、10年ルールの影響をできるだけ少なくする方法について考えてみましょう。
1.iDeCoを年金形式(分割受け取り)にする
一時金ではなく年金として受け取れば、「退職所得控除」ではなく「公的年金等控除」が適用され、10年ルールから逃れることができます。
例えば、60歳から64歳までの5年間でiDeCoを受け取れば、その間は公的年金をもらっていないので、「公的年金等控除」をフルに受けることができます。そして、65歳でもらえる会社の退職一時金には、退職所得控除をフルに使うことができるという訳です。
2.iDeCoを一時金+年金併用にする
一時金で受け取る部分を抑え、残りを年金払いで分割受け取りにする。
iDeCoの一時金部分を抑えると、会社の退職一時金と合計しても、退職所得控除の範囲内に収まる可能性が高くなります。
会社の退職一時金の受け取り時期を名実ともに70歳以降にできない限りは、退職所得控除と公的年金等控除の両方をうまく活用して、できるだけ税額を少なくする方法をとるしかないということです。
「iDeCo受け取り時の10年ルールとは?」と同条件で考えると、
65歳時点の退職所得控除額は2410万円なので、iDeCo受け取り金:2000万円のうち、410万円を65歳に一時金でもらい、会社退職金:2000万円と合算すると、退職所得控除が目いっぱい使えるので税額はゼロ。
残りのiDeCo受け取り額:1590万円を60歳から79歳までの年金払いにすると約80万円/年となります。
そうすると、
60歳から64歳までは公的年金等控除が60万円/年、
65歳から79歳までは110万円/年なので、
前半5年が課税所得計100万円、
後半15年は課税所得ゼロになります。
最小所得をベースに見積もると税額は約15万円。
これは一例ですが、工夫の余地はありそうです。
会社員にとっては10年ルールは「改悪」には間違いないけれど、その中でも少しでも税負担を減らす手段を探っていくしかないと思われます。